page 1
|
2004ツール・ド・おきなわ参戦日誌
2004/11/14 市民レース120kmの部 レース直前の度重なる体調不良についてはWebで詳細にアホさらしなことを書いたので、何名かからお気遣いの声を頂いた。意外にもその誰ひとりとして、「出場を諦めたほうがいいのでは?」などという野暮な助言を下さる方はなく、レース復帰を祈ってくださるので、おかげさまでおきなわへ向けて心置きなく準備せざるを得なくなった(行きたいのか止めたいのかどっちなのだ?)。  ただ直前になるまで本当に行ける身体かどうか自らが一番信用してなかったため、積極的に準備もせず、前日慌てて荷物をまとめる羽目になった。二週間振りのボーボーに生えたスネ毛剃りに30分かかり、睡眠不足のまま羽田へのリムジンバスに乗る。バス1本で出発ロビーまで行けるのは便利で快適、しかも速く、電車を乗り継いで行くより3-40分は短縮される。かかりつけの病院に、搭乗口ロビーから白々しく診察キャンセルの電話を入れる。ストレスのたまる機内サービス攻撃から身を守るため寝たふりで抗戦するが、ジャンボの出来の悪いシートのお陰で実際一睡もできず(ありゃ拷問だ)、飛行機はやや遅れて那覇に到着。高速バスの乗り継ぎに失敗して1時間を無駄に過ごす。沖縄は、期待したほど暑くは感じなかった。 ただ直前になるまで本当に行ける身体かどうか自らが一番信用してなかったため、積極的に準備もせず、前日慌てて荷物をまとめる羽目になった。二週間振りのボーボーに生えたスネ毛剃りに30分かかり、睡眠不足のまま羽田へのリムジンバスに乗る。バス1本で出発ロビーまで行けるのは便利で快適、しかも速く、電車を乗り継いで行くより3-40分は短縮される。かかりつけの病院に、搭乗口ロビーから白々しく診察キャンセルの電話を入れる。ストレスのたまる機内サービス攻撃から身を守るため寝たふりで抗戦するが、ジャンボの出来の悪いシートのお陰で実際一睡もできず(ありゃ拷問だ)、飛行機はやや遅れて那覇に到着。高速バスの乗り継ぎに失敗して1時間を無駄に過ごす。沖縄は、期待したほど暑くは感じなかった。 名護市中心部 名護市中心部那覇空港から名護までの高速バスの旅は、運転手や現地の乗客のやり取りにおおらかでアバウトな土地柄を目の当たりにする2時間だった。沖縄は、多分何でもOKの国だな、とそこで学習する。隣席になった、同じく一人で参加の人と少々会話をするが、お互い初参加でロード初心者でもあるので何もネタがなく、静かに時は過ぎる。名護のレース会場は、都合よくバスの停留所の前にあった。補助席のお婆ちゃんと別れの挨拶をしていると、隣席の彼がオクマまで自走する僕のプランに乗っかりたいと言う。  選手受付を終えて、日没まで時間もないのでさっさと今日の宿泊地オクマリゾートを目指す。 選手受付を終えて、日没まで時間もないのでさっさと今日の宿泊地オクマリゾートを目指す。距離は30kmほどあるので、荷物を全部背負った状態では結構大変。そういう想定で来ていない彼はもっと大変である。ところがその人が前に出ると、やや向かい風の中35km/h以上で飛ばし始めた。ついていくだけで精一杯だ。そのうちに、彼のハンドルの上に無造作に乗っけていた輪行袋が垂れ下がってきて一旦スローダウン(無茶です)。見ると顔中汗が噴出しているじゃないですか。「ちょっとペース速すぎっすよ」と一応言ってみる。 考えてみれば病み上がり(というか治ったと言えるのか?)の初ライド、様子を伺いつつ慎重に行きたい。ところがPRINCE-SLに乗る彼は、このあとホテルに荷物を置いてスタート地点まで下見するという。オクマからゆうに10km以上あり、7km区間は延々の上りだ。「えっ、僕は止めとこうかな」と言うと、「マジっすか?」と静かに驚きの顔を隠さない。そりゃこっちのセリフでござんす。ひょっとしてこの人、スンゲー大物かもしれぬ。結構なふくらはぎの形をしているし。 オクマでのんびりとチェックインしている間に午後5時を過ぎ、試走は諦めたが、明日の補給類を手に入れることも止めてしまったのは失敗だった。練習でも事前の補給は欠かしたこともないのに、なぜこの大事なレース前にスポーツドリンク一つ買う気にならなかったのか、今もってナゾだ。日は落ちてあたりは真っ暗闇になり、もはや近くのコンビニへも買いにいけなくなった。 コテージタイプのオクマリゾートはなかなか雰囲気がいい。野郎同士の相部屋というのは実に似つかわしくないが、レースに憂かれ気分は禁物、レースじゃない時に来よう、ってそれはいつだろう? 中華のバイキングで夕飯をとると、大して食べてないのに腹いっぱいになり(珍しい)、21時には寝てしまった。部屋の人はみなまじめで好かった。 11月14日(レース当日) 暑いのか涼しいのかよく判らない寝苦しさを覚えつつ5時半に起きる。6時頃から朝食をとったが、これまた珍しく腹が減ってない。なかなか食えずに難儀する。緊張しているのかな? 7時前にチェックアウトし、バイクと荷物はトラックに預け、生身の人間はバスでスタート地点に運ばれる。直前になって自販機でアクエリアスを1本買った。これと、参加賞で貰ったパワージェル一つが僕の今回の補給である。なんてしょぼいんだろう! スタート地点の普久川(ふんかわ)ダムは標高350mほどのコース中最高地点をちょっと過ぎたところにある。バスがウンウン唸りをあげてこのコースを登っていく。数人、自走する人を見かけた。僕も当初は自走する意気込みだったのだが、いまはそんな気はさらさらない。 バイクを受け取り、コース上をちょこっとアップしたら早速心拍数が150以上に跳ね上がる。ポルシェ並みに吹けのいいエンジンだね。と言いたいところだが、単に調子がヘンなだけだろう。早々と終了してスタート待機する。長い間待って、ようやくチャンピョンクラス200km集団が怒涛の速さで駆け上がって行った。いつもながら、信じられないスピードだ。 スタート ジュニア120kmがスタートしてさらに数分後、やっと「市民120kmの部」のスタートが切られた。かなり上り傾斜のかかったエリアなので、のっけから多くの人がクリートをはめるのに苦労して周りで罵声が起きる。「行って行って!」とか言っている。慌てんなって。 だが、そういう自分はというと先頭集団に遅れまいと早速マックスパワーで駆け上がる。上り区間はわずか数百メートルで終わるのだが、信じられないことに、ここで一度脚が売り切れた。 マジすか! 当然ながらここからは結構な下り基調で、唯一下りにかけては対等に走れる自信があったのだが、集団は容赦なく飛ばすので下りだろうとマックスパワーだ。ふとPOLARを見ると160bpmを越えている。いかん、レッドゾーンじゃないか。しかも下りで? 200人以上の大集団がぞぞぞーっと下る様はなかなかスリリング。前方でガゴーンとものすごい衝撃音が聞こえた。なんだろうと思っていると、コーナーのイン側のガードレールの向こうに人が見えた。どうやら自爆したらしい、このスピードで! 大丈夫だろうか? いくつかの小刻みなアップダウンをこなし、集団にへばりつきながら10数キロ行くと、「奥」と呼ばれる最初の難関がある。正確には「奥」の一つ手前の上り区間で、トップ集団とはお別れした。「トップ集団」というと聞こえが良いが、「ほとんどすべての選手」とも言い換えられる。蛇行しそうな速度で上りきったところで、前後には誰も居なくなった。いきなりの一人旅。おいらのツールドおきなわはたった20kmで終わってしまった。なんという味気なさ。 いや、実際のところ、そんな簡単に諦めた訳ではないのだ。もう限界というところまで踏んで、それでもついていけなかったのだ。切れる寸前、記録史上初の170bpmを出していたことからも、その苦労の一端が伺えるというものだ。こんな値は、出そうと思ったって出ない。 まざまざと脚力差を思い知らされ、まだ始まったばかりのこのレースをどう組み立てていけばよいのか途方にくれつつ、奥の峠を下る。おきなわのコースは、下りはすべてコーナーが緩く、ノーブレーキで下れる。この奥を過ぎると、しばらくはフラットな海岸沿いの道に入るが、ここでは「集団で走るべき」と先人の誰もが言っているところ。 驚いたことに、まだ後ろに選手がいた。15人ほどの比較的大きな集団にタイミングよく飲み込まれる。ほっと一安心して、この集団で平坦路を飛ばす。最初の頃は30km/h前半ののんびりペースに、どうしたものかと悩んだが、徐々に40km/h以上になってついて行くのもちょっと辛いくらいになってきた。どういうわけか、顔見知りらしい3,4人のみで先頭交代しているようで、僕のいる後ろまでは全く役が回ってこない。そしてなぜか、チャンピョンクラスも一人混じっていた。 このときの心配の種は、次のダム湖への上りでこの集団に着けるかどうか、ということ。いや、彼らは僕より遅く来たのだから、上りでもペースを合わせられるはずだ、などと色々考えているうちに突如道は左に折れ、レースのハイライト、普久川ダム上り7kmへと突入する。 嬉しいことに、その読みは当たって何とか集団前方でペースを維持できる。しかも、「トップ集団」からこぼれてきた人もちらほら見かけるようになってきた。7kmという長さもさほど苦痛には感じず終えようとしていた。まだまだ捨てたものじゃない、と思いはじめたその矢先。 右足ふくらはぎが強烈につり始めた。まだコースの半分も来てないのに、変調を来たすのがあまりに早すぎる。攣っていては何もできず、集団に先行を許し、どんどんスローダウンする。 攣る原因は第1に脚力不足、第2には脱水症状に陥っていたことも否めない。 ボトルは前述したとおりアクエリアス1本のみで、ちょうど飲み干した頃だったが、それ以上に暑さが堪えていた(POLARによるレース中の気温は平均26℃、最高32℃を記録した)。頭から水を浴びたい気分だったのだが、そのためのボトルまでは計算に入れてなかった。また、今回失策の一つがウエアだ。気まぐれで持ってきていた春秋用のウエアが、「こっちの方がピッチリしてカッコいいかも」というつまらない理由で選択されていた。袖はジッパーで取り外し可能で半袖になっていたが、表面はウインドブレーカ生地で、中は少しモコモコしている。これが暑かった。こういう、救いようのないアホな考えが今回多すぎる。 コース上に2箇所しかない補給地点の一つ目(=普久川関門)を1:37:02で通過。水とスポーツドリンクを貰った。ところがこれがとんでもない代物だった。まず、どちらのボトルも半分くらいしか入っておらず、水の方はボトルの口の閉まりが甘くて、飲んでる途中でガバっと開いて一気にこぼしてしまった。もう一つの方もやはり、飲む度にどこからともなく漏れるのだ。というわけで、貰った水分はその後10km以内に全部飲み干すことになる。 ココからはまたアップダウンが続く道となる。高低図を見た限りじゃ何てことないだろうと高をくくっていたが、普久川ダムを上った時点で獲得高度は半分しか消化してないのだから、この後のアップダウンがいかに身にしみるか、推して知るべしであったのだ。だがその割には、ここへ来るまでに体力を使い過ぎていた。もはや殆ど残っていない状況にあった。そしてそれに追い討ちをかけたのが、水分補給の失敗。次の補給地点まではまだかなりあるが、既に喉はカラカラである。自販機を横目に見ながら、「ああ金持ってくりゃよかったな」などと思う。ロードレースの最中に自販機のジュース買う奴っているんですかね? 水分不足の為に次から次へとあちこち攣る。すぐに反対のふくらはぎが攣り、太腿が攣り、さらにはハムストリングスまで攣った。もう両足で攣ってないところはない、というくらい見事に攣ってしまった。脚をまげることも伸ばすこともできない、などという状況にも陥る。オレって攣りの天才だね。まさしく、攣りバカ日誌じゃないか、などと、我ながらうまいことを考えたな、と思う。 うまいか? メーターを見るとまだ60kmなどというのどかな距離を示している。それなのにこの辛さは一体なんだ? たかだか60kmでこんなにひどい走りをしている自分が情けなかった。ちょっとした上りでヘロヘロ、これじゃママチャリに乗る一般の人より遅いぞ多分。 「おっ、いいクルマにのってるねぇぇぇ」と嬉しそうな声で抜かしていくオヤジ。「すみません」となぜか謝る。いや、きっとおいらはこのTIMEに謝ったのだ。ご主人様の腑甲斐なさで恥をさらしつづけている。甚だ申し訳ないの心。オヤジのすぐ後についていた人が「平良(たいら)まで一緒に行きましょう」と呼びかけてくれた。その一声に励まされ少し活力が湧いてついていこうとする。しかし、なぜ「ゴールまで」じゃなくて「平良まで」なんでしょうか? 平良には関門がある。ま、そういうことでしょうか。 平良どころか、さっさと千切れてしまった。彼は正しい。 しばらく行くと、海岸沿いの道は平坦区間となる。ここでもラッキーなことに、市民200kmのこぼれ組15名ほどの集団に乗ることができた。別のカテゴリーの集団に乗ることは控えなければならないが、120kmの人も混じっていたからカンベンしてください。 というか、そこでついていけたのは平らな部分2,3kmだけだったが。 平良の関門を通過する。ここでは、1位通過のタイムが掲示板に記されていることに気づいた。120kmのトップ通過タイムと、自分のタイムを比較する。絶望的なことに、30分は離されていた。一応、ルールでは「トップ10位集団から15分遅れた選手は失格」となっているのだ。 まあでも行くしかない。 この頃になると心拍数は低いままのことが多くなってくる。疲れるということは力を入れられないということだ。水が欲しくて朦朧としている。すぐ攣ってしまうので全力で走れないのも事実。さらには、ダンシングを困難にしていた。信じられないことに、サドルから腰を浮かした状態で身体を支えるだけの筋力が脚に残っていない。いま自分で書いていて、「そんなことってありえるのか?」と思うけど、ホントにそうだった。悲しすぎる。くどいようだが、まだ80km付近である。 やったぞ! 第2の補給地点がやっと巡ってきた。これをどれほど待ち望んだことか。今度こそボトルをしっかり3つとり、一つはすぐさま飲み干す。攣りバカも限界にきていたが、水分補給で幾分復活した。この後は最後の難関、源河(げんか)の峠だ。 この峠の標高はもちろん普久川ダムよりずっと低いのだが、僕にとっては桁違いに辛い上りとなった。さすがにここは皆辛いらしく、応援の人もチラホラ見かける。「頂上までもうすぐだよぉ〜」の声に何度騙され失望したか分からない。そういうイイカゲンな情報は流して欲しくないものである。大した傾斜ではないのだが、ジグザグに蛇行して上っている人が多い。でも、朦朧とした状況下でそれをやると逆行しそうになるので、僕にとっては禁じ手なのである。 この緩い坂を死にそうな形相で上っているおいらの、いったいどこに存在価値があるだろう? 走ることの意味って何だろう? アホなことばかり堂々巡りで考える。 だがホントは答えは決まっている。存在価値などないのだ。あったりめえじゃねえか! こんなに遅いんだよ! でもなぜ人は考えつづけるのか、きっとどこかに価値があるはずという甘い期待を未だ捨てきれない証拠に他ならない。 その甘い考えは、赤い旗で振られて、ゲートを封鎖されるまで消えないものなのであろう。源河の関門でまさかの、いや、当然の降車指令。レースは終わった。お疲れ様です。ここまでのトリップメータはちょうど100kmを示していた。平均速度は28.9km/h、完走はとても無理なスローペースだ。 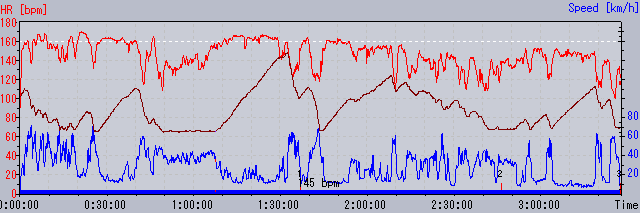 脚切りは参加前から覚悟していたことではあったが、いざ直面するとそれなりに落胆は大きい。だがそれ以上に、安堵感の方が強かった。それくらいクタクタだったし、自分の腑甲斐なさを誰よりも痛感していた。休むことを許されたら、途端に両足は痙攣して、なかなかペダルから足を外せなかった。バイクはその場に放置し、収容バスにのってゴールを目指す。結構大勢いたので、照れ臭さもさほどなかった。トライアスロンから比べたら完走率は著しく低い。 考えてみたら、数々のレース歴の中で、途中リタイヤとなったのはこれが初めてであった。 |
||