|
ツインリンクもてぎ100kmサイクルマラソン2005参戦日誌
昨日の夕方から暖かい南風が激しく吹いていて、朝5時に家を出るときも風ビュービューで気温は13℃もある。首都高にのると、追い風のため瞬間燃費計は20km/lあたりを示しながら走っている。ところが、柏に入った頃から急変。いきなり3℃以下になる。なんだこの温度差は?2005/1/4 栃木・ツインリンクもてぎ 100.8km 水戸ICで降りて茂木を目指す。大晦日に降った雪が、融けずに野原を白くしていた。どこの雪国に来ちまったんだい? 途中、何箇所かの凍結路を慎重に進みながら、ようやくツインリンクに近づくと、ギョエー道路に雪がこんもり積もったままだ。外気温−1℃で、間違いなくアイスババ―ン。20km/hの超ビクビク運転。時々ズリっと車体が横を向く。いまのは10度くらい向きが変わったぞ? 幸い下り区間だったので惰性で走れたが、逆方向はまず登れまい。帰りはどうすんだぺ? 全身硬直状態の運転に疲労を覚えつつ、7時半にもてぎ着。第1パドックは既に満車で、遠い第4パドックに誘導される。何で第2パドックは解放してくれないんだろ。  コース上もやはり路面が凍っているらしく、その解凍作業でスタートが大幅に遅れそうである。巨大バーナーで凍結路面を熱している。お陰でローラー台アップも余裕ですることができた。遥々第4パドックまでryuさんが声をかけてきてくれて、しばしご歓談。今年もよろしくおねがいしますです。 コース上もやはり路面が凍っているらしく、その解凍作業でスタートが大幅に遅れそうである。巨大バーナーで凍結路面を熱している。お陰でローラー台アップも余裕ですることができた。遥々第4パドックまでryuさんが声をかけてきてくれて、しばしご歓談。今年もよろしくおねがいしますです。1周だけ試走し、トイレには2度行き、9:40の召集時刻となったのでスタート位置に向かう。急に気温も上がってきて、風は無く、昨年よりも穏やかな気象条件は全くもってとことんついている。ブレスサーモ、Piの冬ジャージ、BLBジャージの3枚重ねでちょうど良かった。 昨年より参加者は200人ほど少ないようだ。MTBや小径車がいない分だろうか。スタート位置は相変わらず後ろの方で、のっけから集団に着けない、という昨年の二の舞はぜひとも避けたかったが、横にryuさんもいるし、何とかなるでしょ、と不安と期待が入れ混じる。トイレにまた行きたくなってきたがもう遅い! スタート1分前、Polarのスタートボタンを押すと、心拍をキャッチできない! どうやら、過密状態にある周囲のいろんな電波を受けて、どれがどれだか分からなくなっているようだ? ヤバイ。 教訓:Polarはスタートラインに並ぶ前に計測開始せよ。 あれ? 常識でしたか。すんでのところで、信号を無事拾ったようだ。 予定より90分も遅れての10時にレース開始。 例によって、ノロノロと混雑状態の集団が進み始めた。 
2周目、さてここからが本当のスタート。昨年は巨大先頭集団に、Lapされた後で2周ほど喰らい着いて、あっさり千切れた。尋常でないスピードが印象に残っている。 ところが、実際に最初から先頭を追って走っていると、格別に速いという感じもなかった。昨年より遅くないか? と何度も思う。やや拍子抜けだ。だが、かなりの人数がごっそり固まっているので、群集の恐怖を感じる。誰かがコケたら、将棋倒しで全滅するんじゃないかというイメージが頭を過ぎる。 このコース一番のガンバリどころはトンネルを抜けてからの上り区間、特に図中B辺りだろう(あたり前すぎ)。この付近は眺めもよく、登り斜面に続く道と、周りを埋め尽くす雪景色は、一瞬、森林限界を超えた山岳コースのひとコマを思わせる。 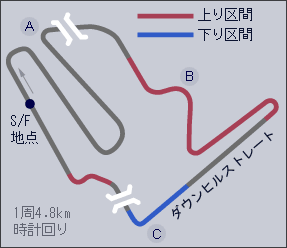 グヘッ、やっぱり辛いや。心拍もレッドゾーンの160を超えている。この強度をあと19回繰り返せるかどうかにかかっているのは間違いない。フライトデッキ君はケイデンス表示に切り替え(スピードは集団任せなので見てもしょうがないっしょ)、100rpm前後でシッティングで行く。このガンバリどころの上りは、少しく息抜きしたあと、ダウンヒルストレート手前のヘアピンまで続く。 グヘッ、やっぱり辛いや。心拍もレッドゾーンの160を超えている。この強度をあと19回繰り返せるかどうかにかかっているのは間違いない。フライトデッキ君はケイデンス表示に切り替え(スピードは集団任せなので見てもしょうがないっしょ)、100rpm前後でシッティングで行く。このガンバリどころの上りは、少しく息抜きしたあと、ダウンヒルストレート手前のヘアピンまで続く。2周目を終え、ラップタイムを見る。6分45秒。あれ、昨年はどのくらいだったっけ? 結果的には、この2周目が最速ラップだったのである。 集団の頭から20m以内に常に着くように心がけた。この辺りはまだ横幅2,3列程度で、大抵片側が空いている。後方は昨年の経験から多分アコーディオン効果で速度差が激しい。風除けのメリットより速度差のデメリットのほうが大きいと考えたのだ。先頭は大抵5,6人位までが1列棒状になっていて、実業団レベルが引っ張っているように見受けられた。ま、僕なんかは到底お呼びでないから、義務感に苛まれることなく温存走りができる。実際、意図して先頭まで上がっていくとしたら、かなりのあいだ風と向き合わなければならないのだが。A木さんが似たようなポジションにいる。後ろから見ると筋トレで鍛えた蓮根のように隆々とした脚が特徴ですね? それでいて(?)かなり回転系のようだ。 走り出して、これは暑いと感じたのか、上着を脱ぐ選手まで現れた。集団走行中に手際よくジャージを脱ぐ。余裕なところを見せつけられちまったぜ。だが、真似できねー。 昨晩の、冷凍ピラフ+赤いきつね+キナコ餅カーボロードはうまく機能している。今朝はおにぎり二つと豆乳、ボトルにはクエン酸入りBoneEnergyが満たしてあった。ダウンヒルストレートで飲む。 そんなこんなで、早くも6,7周あたり。だんだん、上り区間が厳しくなってきた。この集団に着けるのも10周が限度だろうか。だが、周回を重ねるうちに気づいたこともあった。 いままで集団走行といえば、前方と少しでも距離が開くとアクセル全開、追いついたらブレーキ、その繰り返しという、せっかち野郎の渋滞走行さながらであった。だが、そんな運転は燃料の無駄遣いである。千切れることへの不安から目一杯踏んでしまうのだが、これでは体力の消耗が激しい。実は、周囲の状況をもっと広く把握しておけば、ラフな加減速でも千切れるなんてことはないのだ。さらには、千切れる時というのは同時に限界状況という伏線があり、余裕があるときは仮に千切れてもすぐ追いつける。 そう気づいてからは、スロットルの開き加減を努めて最小に抑えるようにした。ロードレースでも低燃費運転は必要なのである。1年間やってきて、初めて意識したことだった。 ヘアピンカーブの直前、直後はスピードの変化が大きい。例えば図中Aのコーナーは結構きついので、その手前のストレート区間でかなり減速がある。コーナーの立ち上がりで集団がワッと加速するのだが、ここで意気込んでムチを入れすぎると、そのすぐ後に訪れる上り区間で売り切れてしまうので、穏やかに加速する。どうせ皆、大した加速はしてないんだって。 さらに、もっと極端なのが、図中Cのダウンヒルストレート後の下りカーブ。昨年も思ったけど、ここのコーナースピードは集団では遅すぎる。まずもって、ここのコーナー手前でブレ―キングなんてほとんど要らないハズだと思うのだが、現実は皆ギュルギュルとゴム臭さが漂うくらい減速する。どうしてなのか説明がつかないんだけど。 コーナーが終わると、今までの抑制の反動が出るのか、皆ダンシングでぶっ飛ばす。なぜ毎回このトンネル内でシャカリキになるんだ? 実は、そのあとのS字カーブで混雑して、上りにも関わらず惰性で追いついてしまうのだ。だから慌てなくてもいいのである。 そうしてなるべく温存した走りを心がけ、唯一きついB地点でヘタレないように集中して走ることを心がけた。 9周目、トップの誰かが背中から補給食を取り出したのだろう、それを真似る人がいたるところに出現。トップが補給タイムをとるってことは、後ろも休みってことか。それにしても、皆さんポッケに固形エネルギーをたらふく携帯していますね。アンカーのプロ選手も3,4個持って、しきりに食ってた。何一つ持たなかった僕は道に外れたことをした気分。 上り区間も平和に過ぎる。すると、ラバネロの親分っぽい人が頭から降りてきて、仲間に向かって「○○○、もっとポジション上げとけ! 今は中だるみだから、次の周はペース上がるぞ!」とハッパをかけた。 なるほど。でもそういう作戦指令は、そんなでかい声でなく、もっと小声で伝えて貰わないと困ります。周囲は皆、フムフム、ポジション上げとくか、と聴いていたに違いない。それとも集団全体のスピードを底上げしようとする巧妙な心理作戦だったのか? トップまでは結構距離があるので、それが本当の第1集団なのか、それとも逃げ集団が別にいたのか、よく分からないし、関心もなかった。一時的に数人の逃げ集団ができたらしいが、再び吸収したりして、大きな逃げは成功していない模様。その判断の決め手は、先導のオートバイのエンジン音だったかもしれない。 ふと見ると、先月の下総レースで一緒に走った覚えのあるアンカーの人が混じってた。ああ、特長あるフォームのこの人だ、後で名前を確認するためにゼッケンを覚えておこうと思ったが、ヘルメットに貼ってない。はがれたのかな? とのん気なことを考えているおいら(招待選手です)。 落車は結構発生した。まず危険地点は上りのB付近のインコーナー。S字カーブ途上のためか、集団がイン側を圧迫する傾向があり、一番インにいる人が進路を阻まれる。コースのすぐ外が固い雪の絨毯なので逃げ場がなく、転倒。 とに角、イン側は危ない。よそ見してうっかりコースアウトして、雪の中に突っ込み、反動で集団内に跳ね返ってくる死神のような奴もいた。 コース幅が十二分に広いという平穏かと思える条件も、落車の原因の一つではないかと思う。コース中央を走っていると、そこがコーナー途中なのか直線部分なのか、瞬間的に分からなくなることがある。視野の中に、道の形状を把握するガイドラインが入ってこないためだ。特にスタート地点から2つ目のコーナーは複合Rになっているので進路を誤りやすく、最悪斜行する羽目になる。 ラバネロの親分の予想は懸念したほどではなく、集団のスピードに急激な変化はない。後ろがどっぷり追いつきすぎて過密状態になることもあった。だが、上り区間では徐々に周囲に疲れが見えて取れた。そういう自分も、15周目過ぎ頃から、今までとは異質な疲れ方になっている。こんどこそやばいかも。徐々に、あと何周? ということが気になりだした。ラストまで持たない、という不安が膨れ上がってきたのだ。集団はいつラストスパートに入るのだろう。 しばらく見なかったA木さんがひどく疲れた形相で声をかけてきた。顔はびっしょり汗をかいている。ご多分に洩れず、しばし先頭で積極的な走りをして、かなり消耗したらしい。ウヘ―真似できません。A木さん、その後もまた姿を見なくなったが、後で聞いたらなんと落車に巻き込まれたとのことで、残念、ついてなかったですね。 ラスト周回のジャンを聴き、集団は活性化する、かと思われたがさほどでもなく、でもちょっとぴりぴりした雰囲気。いや、一番ぴりぴりしてたのは自分だったかもしれない。前走者にハスりそうになり、慌てていることを悟る。B地点の上りで少しずつ前へ移動。ダウンヒルストレートの遅い下りコーナーではこのときとばかりアウトからゴボウ抜きしてやろう、と前々から決めていたが、うっかりしていた、今いる位置はインベタだ。一か八か、インから追越をかけ、とろい奴を僅差でかわし、周回遅れで混雑するS字カーブも暴走(あぶねェ奴でスミマセン)。あとはフィニッシュまで直線のみ、という段階にきて、ふとやる気がなくなる。 いままで一度たりとも先頭を引かずして、最後にちゃっかり少しでも着を狙おうだなんて、虫が良すぎやしませんか、おやじ〜? という気持ちになったのか、それとも、そういうことにして、実はすでに売り切れてラストスパートなんぞ無理なのを都合よく別の理由で納得しようとしたのか。 まあでもおざなりにスパートして、ゴォール! これにてお終い。 トップとは10数秒差でゴールしたらしい。 後で確認したら、フィニッシュの瞬間スピードは32km/h。今までここは40km/h前後で通過していたから、ラストスパートどころか、大いに減速していやがるのはどういうこと? やっぱりマジ売り切れてたのかもしれん。 その後、表彰式会場にてビックラこいた。 下総でも一緒に走ったというアンカーの選手とは、アテネ五輪にも出た田代選手とのこと。どひゃーっ、マジかよぉー。 もしかして、ラバネロの親分というのは、飯島選手? 不勉強極まりなくて、どうもスミマセン。 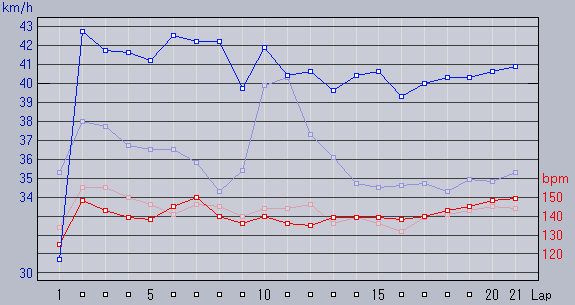
ラップ毎の平均速度と平均心拍数の推移 (薄色は昨年のデータ) 記録 2:30:11.622 総合トップとの差16秒
総合23位/606人中 男子C(36-45歳)7位/179人中 1746kcal 気温 9-12℃ 昨年と比べたら、上出来の結果なんだけど、何かしっくり来ない。 心拍データが証明している通り、小集団の先頭をよく走っていた昨年より楽をしたんじゃないかな。昨年の自分のほうがずっと頑張ったような気がしてきた。かといって、先頭を仕切るような器でもないし、その意義もよくわからない。果たして、来年は何を目標に走ったら良いのか。いっそのことDHバーを装着して単独で走る、というのも良いかも。 |
||